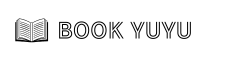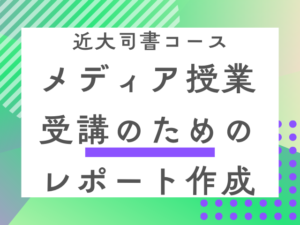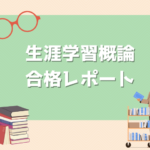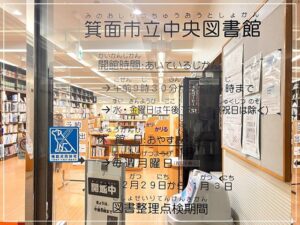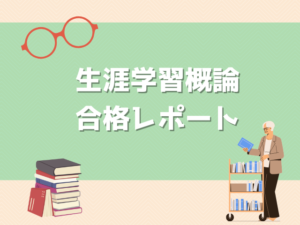近畿大学図書館司書「児童サービス論」の合格レポートです。
設題1のみのレポート内容となります。
少しでも参考になれば嬉しいです。
**書きうつし厳禁!**書き写しは大学から除籍される可能性もあるため絶対にやめてください。あくまでも学習の参考に。
「児童サービス論」レポートの設題
「児童サービス論」レポートの設題です。
- 図書館における直接(的)サービスと間接(的)サービスの意義と方法について述べなさい。
- 図書館におけるヤングアダルト・サービスの意義と実践方法について述べなさい。
「児童サービス論」のレポート作成上の注意点・ポイント
「児童サービス論」のレポート作成上の注意点とポイントです。
- 1900字以上書くこと
- テキストを読み、参考文献で肉付けする
- 必要以上のコメントや感想は不要
- 必ず参考文献をあげること
テキストはもちろん、参考文献等をつかってレポートを作成することが求めれています。
「児童サービス論」の参考書等の紹介
紹介されていた参考文献はできるだけ読むようにしました。
私自身に子どもがいたため、どの本も面白く、参考になりました。
【入門的なもの】
- 堀川照代編著『児童サービス論』日本図書館協会
- 赤星隆子他『児童図書館サービス論』理想社
- 笹倉剛『心の扉をひらく本との出会い』北大路書房
(その他)
- リリアン・H.スミス『児童文学論』岩波書店
- アイリーン・コルウェル『子どもと本の世界に生きて』こぐま社
- 石井桃子『新編 子どもの図書館』岩波書店
- 瀬田貞二『幼い子の文学』中央公論新社
- 笹倉剛『感性を磨く「読み聞かせ」』北大路書房
「児童サービス論」合格レポート
直接的サービスとは(431文字)
本を読んで聞かせたり、お話を語ることなどで直接的に利用者と本をつなげる読書活動である。代表的なものとして「読み聞かせ」や「ストーリーテリング」などがある。
これをきっかけに子ども達が図書館の本にふれ、読書の面白さを知ってもらうことが目的である。
直接的サービスには子ども達の物語を聞く力、本への興味や関心、感性を育成する効果がある。
「読み聞かせ」は本を声に出して読んで人に利かせる活動であり、字の読めない幼い子どもに対してだけでなく、大人も耳から読む読書体験を楽しむことができる。
「ストーリーテリング」は話し手が物語を覚えて語る方法で、聞き手は語り手から聞く物語を自分の頭の中で組み立て、想像力を持って解釈していく楽しみがある。
語り手によって同じ話でも違った味わいを持たせることができ、音としての言葉の魅力を感じたり、人と人とのコミュニケーションを体験できる。
ほかにも「紙芝居」や「おはなし会」「ビブリオバトル」など様々なサービスが展開されている。
間接的サービスとは(541文字)
間接的サービスとは、子どもと本を結ぶための読書環境整備に関するもので、具体的にはテーマ展示や年齢別のお薦め本のリスト作成、調べ学習用のパスファインダー、目録・索引づくりなどがある。
展示は子どもに興味と関心をおこさせ、「図書館は楽しい場所」と言う印象を与えると共に、色いろな本があることに気づかせることができる。
また、図書館員による本の説明やイラストには温かみがあり、本に親しみを持たせることができる。
調べ学習用のパスファインダーは、子どもが主体的に調べることを応援するためのものであり、図書館員は子どもの理解力を考えながら必要な資料の収集を行う。
資料を探すために利用するOPACついては検索方法や操作方法に困っているときにすぐにアドバイスできるようカウンター付近に設置したり、使いやすいように高さにも配慮する。
分類や配架については「あいうえお順」や、おおまかなジャンル分け、表紙を見せた書架、子どもが手に取りやすい低い棚の使用など、一般書とは違う方法で子どもが使いやすい工夫が必要である。
このほかにも図書館員は優れた絵本や児童書を選書するだけでなく、目録作成やバーコードラベルをつけたり、汚れたり破れた本の修繕などもおこない、利用者が使いやすいようにする。
「児童サービス論」レポート作成のポイント
おそらく司書資格取得を目指す皆さんにとって、作成しやすいレポートだと思います。
子ども達にとって楽しく、親しみが持てる図書館とはどういったものか。
どんなサービスを提供すべきか。
とくにヤングアダルト世代の読書離れは問題視されており、参考文献の中でいろいろな工夫が書かれています。
公共図書館での仕事を考えているなら、参考文献を沢山読むことはその後の仕事に直結します。
できるだけ多くの本を読み、理解を深めてみてください。
司書になった時にとても役だつと思いますよ。
頑張って!